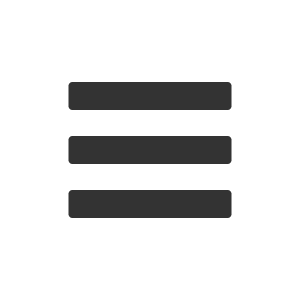京都大の西祐貴助教らの研究グループは、大腸がんの「間質」に多く存在するたんぱく質「THBS2」が免疫細胞による腫瘍内部への侵入を妨げ、がん免疫を抑制していることを突き止めたと発表した。また、マウスを用いてTHBS2の働きを抑えることで、免疫細胞が腫瘍内に呼び込まれて腫瘍が小さくなり、免疫療法の効果が大幅に増強することも確認した。THBS2を標的とすることで、有効な治療手段が限られている大腸がんの克服が大きく前進すると期待されるとしている。
大腸がんは、日本で患者数・死亡数ともに増加しており、新しい治療戦略の開発が強く求められている。治療成績が改善しない要因の1つとして、腫瘍内部に多く存在するがん細胞以外の組織や細胞(がん間質)が、がんの高悪性化や、標準的な治療を一定期間行っても病気が改善しない治療抵抗性に深く関わっている可能性が指摘されている。
がん間質は線維芽細胞や免疫細胞、血管、細胞外基質など多様な成分から構成される組織で、腫瘍の増大や治療効果に大きな影響を与えるが、その役割の多くは分かっておらず治療標的につながる発見は限られている。
研究グループは、がん間質に豊富に存在するTHBS2に着目。ヒト⼤腸がんの公開遺伝⼦発現データベースを解析したところ、THBS2はがん間質が多く、予後が悪いタイプの大腸がんで多くつくられていることが分かった。さらに、がん組織を1細胞単位で解析したところ、THBS2は主にがん組織内の線維芽細胞が産生していた。
また、がん間質が豊富な大腸がんでは、THBS2が腫瘍と正常組織の境界部に多く存在し、がん細胞を攻撃するために集まった免疫細胞「CD8陽性T細胞」が腫瘍内部へ侵入できていない様子も認められた。これらの結果から、THBS2が線維芽細胞による免疫排除の鍵となるたんぱく質である可能性が示唆された。
次に研究グループは、間質が豊富に形成されるマウスモデルを用いてTHBS2の働きを調べたところ、ヒトと同様に腫瘍と正常組織の境界部でTHBS2が多く存在していることが分かった。そこで、THBS2をつくれないマウスに大腸がん細胞を移植すると、形成された腫瘍はTHBS2を正常につくるマウスよりも小さく、腫瘍内部に多くのCD8陽性T細胞が侵入していることを確認した。このことから、THBS2はCD8陽性T細胞が腫瘍内に入れないように働いていることが分かった。
加えて、大腸がんを形成し、THBS2をつくれないマウスに免疫チェックポイント阻害薬を投与すると、THBS2を正常につくるマウスと比べて治療効果が劇的に増強し、ほとんどの腫瘍が退縮・消失した。
これらの結果について研究グループは、「大腸がんが免疫から逃れる仕組みの一端を解明したものであり、THBS2を阻害することで免疫細胞を腫瘍内部に“呼び込み”、免疫療法の効果を大幅に高められる可能性が示された」と指摘。今後について、THBS2を阻害してがん免疫療法の効果を高められる薬剤が開発できれば、手術で根治できない進行した大腸がんへの新たな治療選択肢が生まれる可能性が期待できるとしている。
【関連記事】