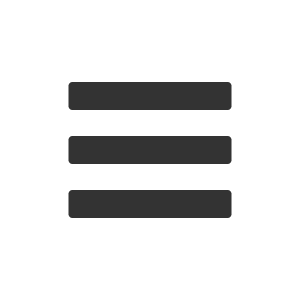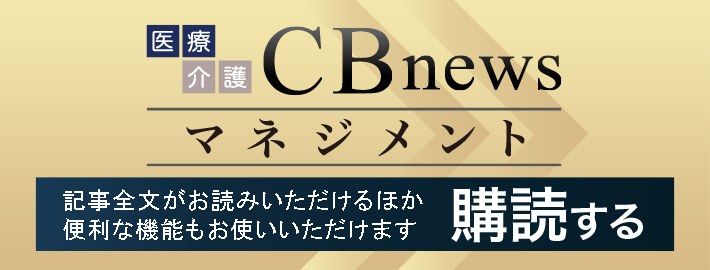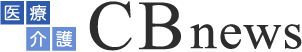第1回「病院DXアワード」(CBnews主催)で、初の大賞に輝く、製品・サービスは-。続々とエントリーが集まる中、4人の審査員に、病院DXへの思いを聞いた。1回目は、病院DXアワード審査員長の東京医療保健大学教授で、日本医療マネジメント学会DX委員長などを務める瀬戸僚馬氏が、病院DXアワードの意義などを語った。
医療におけるDXは、政策と現場の2つの目線があります。政策の目線としては、厚生労働省が定義する「医療DX」です。保健・医療・介護の各段階で発生するデータを通して国民自身の予防を促進し、より良質な医療を受けられるように、社会や生活の形を変えていくというものです。もう1つが現場目線のDXです。
医療現場の問題意識としては、財源が公的か自前かということは置いておいたとして、医療機関自身が生き残りを迫られていることは重々分かっていると思います。生き残るためにいろいろなものを組み替えていかなきゃいけないということも。その手段として、デジタルを活用し、これまでの組織や仕組みを変革するDXがあり、病院経営の土台となるのが「病院DX」です。
経営資源として「ヒト・モノ・カネ」がありますが、例えば「ヒト」だけで考えても病院でのDXは不可欠です。さまざまな職種での人材不足が問題となっていますが、どの職種でも共通しているのはデジタルネイティブな若い人が医療現場で着実に増えています。こうした若い人と、医療業務に長年従事しているベテランとではデジタルに対する温度感があり、それが仕事の仕方に表れ、世代交代に大きく影響します。世代交代が進まなければ、人材が確保できず、特に中小規模の病院では経営が成り立たなくなる恐れもあります。
若い世代の人材確保という意味でもデジタルは重要ですが、これまでの業務にデジタルを取り入れるだけだと、ただ業務が増えるだけです。従来の業務や組織を変革するためにデジタル化を進めることこそがDXです。ただ、DXの重要性は頭では分かっていても、具体的なイメージがわかないという病院の経営層が多いのも事実です。そこでDXに取り組む病院の成功事例が貴重になります。もっとも、DXのベースとなるデジタル製品、サービスの開発や提案は、民間企業が行っており、病院だけでDXは成功しません。同時に、製品・サービスを開発した企業が、自信をもって送り出した製品などであっても、病院から理解が得られなければ、導入は進みません。
企業と病院がタッグを組んでこそ、病院DXが進んでいきます。「病院DXアワード」は、病院のさまざまな課題解決の一助になろうとする企業の製品・サービスにスポットライトを当てる一方で、その製品・サービスが病院現場の目線にあるかを、医療従事者が確認・評価します。病院DXを進める上で、とても意義のある取り組みと考えます。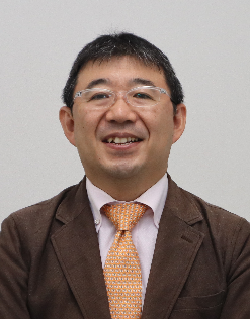 瀬戸僚馬 氏
瀬戸僚馬 氏
東京医療保健大学 医療保健学部 医療情報学科 教授
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科博士課程修了、博士(医療福祉経営学)、津久井赤十字病院(現:相模原赤十字病院)、杏林大学医学部付属病院を経て東京医療保健大学に赴任。保健師・看護師・診療情報管理士・上級医療情報技師育成指導者。大学勤務後も公的病院の再整備事業評価委員や民間病院の顧問などを歴任。日本医療マネジメント学会DX委員長、日本医療情報学会医療情報技師育成部会教科書委員会総括委員長、日本レセプト学会学会長など。著書に「看護DX実践ガイド」「医療経営士中級テキスト 医療ICTシステム」など。
(残り0字 / 全1451字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】