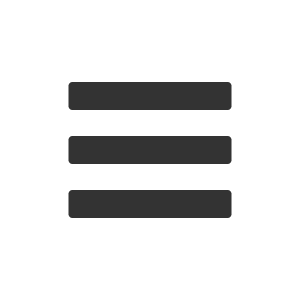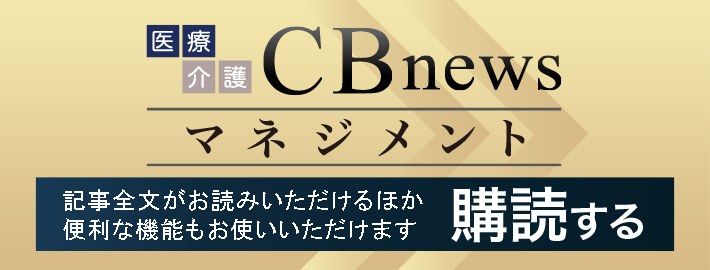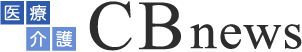CBnewsでは、医療経営の厳しい現状や国への要望を病院のトップから募り、緊急寄稿として配信する企画をスタートさせた。第1弾は、総合大雄会病院の高田基志院長。今後も随時配信していく。
【社会医療法人大雄会総合大雄会病院 高田基志院長】
日本病院会など6団体が今年3月に発表した「61.2%の病院が赤字」というデータを、世の中の人はどう受け止めているのだろう。「ある日突然、病院がなくなります」と警鐘を鳴らしてはいるが、どこか人ごととして、あるいは遠い未来の話として捉えてはいないだろうか。「61.2%が赤字ならば、残りの4割近くの病院は黒字だから問題ないのでは?」と考える人もいるかもしれない。そもそも、「病院が金もうけをすること自体いかがなものか」と考える人もいる。かつて、お金に細かい医師のことを「医は算術」などとやゆされたものだが、今や本来の意味である「医は仁術」では病院は存続できない。人の命を救うはずの病院が、経営的な死を迎えつつある。 こんな話も聞こえてくる。「病院ってもうかっているんじゃないの? だって、医者は外車に乗っているじゃないか」…と。確かに外車に乗っている医師はいるし、他の業界と比べるとその割合も高いかもしれない。高給取りであることも事実である。しかし、医師が高給取りであることと、病院がもうかっていることはイコールではない。病院経営の特徴は、固定費比率が非常に高いことである。近年のインフレにより、最大の固定費である人件費が上昇し、経営を圧迫している。さらに、変動費である医療材料費の高騰が追い打ちをかけている。一般企業であればコスト上昇分を価格に転嫁することは可能だが、医療ではそれができない。まさに八方塞がりである。
こんな話も聞こえてくる。「病院ってもうかっているんじゃないの? だって、医者は外車に乗っているじゃないか」…と。確かに外車に乗っている医師はいるし、他の業界と比べるとその割合も高いかもしれない。高給取りであることも事実である。しかし、医師が高給取りであることと、病院がもうかっていることはイコールではない。病院経営の特徴は、固定費比率が非常に高いことである。近年のインフレにより、最大の固定費である人件費が上昇し、経営を圧迫している。さらに、変動費である医療材料費の高騰が追い打ちをかけている。一般企業であればコスト上昇分を価格に転嫁することは可能だが、医療ではそれができない。まさに八方塞がりである。
「それなら、医師の給与を下げればいいではないか」と思う人もいるだろう。確かに、下げることは難しくとも、かつてはある程度低く抑えられていた。2004年に初期臨床研修制度が改正されるまで、病院の医師のほとんどが医局からの派遣で構成され、比較的低い給与水準で勤務していた。しかし、これに懲罰的な意味はなく、むしろ医師としての貴重な体験を積むことができるという、何物にも代え難い対価が伴っていた。しかし、今では医師の採用も流動性を増しており、給与の低い病院は見向きもされない。医師は病院にとってプロフィットセンターである。いくら立派な施設があっても、医師がいなければ意味をなさない。医局の影響力が弱まり、医師の確保が困難になった結果、地方の病院が次々と閉鎖されていった背景には、こうした構造的な問題がある。
「ちゃんと黒字を出している病院があるのだから、赤字の病院は努力が足りないのでは?」との意見もあるだろう。確かにわれわれの努力不足も否定はできない。しかし、多くの病院が「何をすれば黒字化できるのか」すら見えず、もがき苦しんでいるのが実情ではないだろうか。であるならば、黒字を出している病院の経営手法を、国が徹底的に調査し、その情報を全国に公開するというのはどうだろう。国も赤字病院の問題点を探るよりも、成功している病院の事例を分析する方がはるかに少ない労力で済む。黒字病院は圧倒的な少数派だからである。
(残り0字 / 全1326字)
【関連記事】