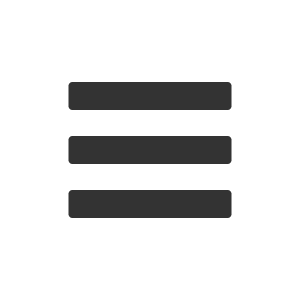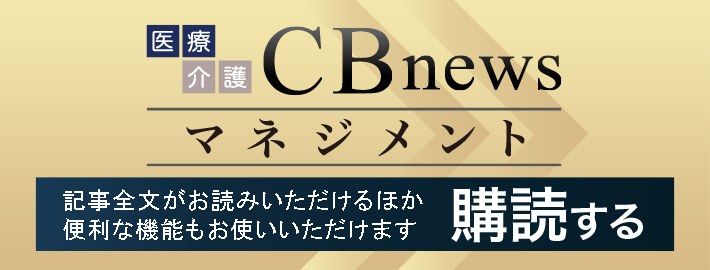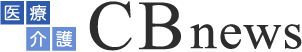【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
介護人材不足と言えば介護職員が足りていないという事態がまず頭に浮かぶが、それ以上に介護支援専門員(ケアマネジャー、以下ケアマネ)が不足しているという事態が起きている。全国社会福祉協議会の中央福祉人材センターが実施した調査の結果によると、今年2月のケアマネの有効求人倍率は9.70倍となり、介護職員の6.13倍を大きく上回っている。
ケアマネが不足している状況は、この調査データを見るまでもなく、さまざまな地域で関係者が実感していることだろう。特に居宅介護支援事業所のケアマネ(以下居宅ケアマネ)の不足は深刻で、それによって重大な問題が起きている。小さな町や村で居宅ケアマネの数が減り、多くの居宅ケアマネが、担当する利用者を限度ぎりぎりまで抱えていて新規の利用者を受け入れられなくなっている。そうした町村では、近隣市の居宅ケアマネに担当を打診するが、打診先でも多くのケアマネが新規の利用者を受け入れられないほど担当人数を抱えていたり、移動距離がネックとなって受け入れを拒否したりするケースが目立っている。そのため、利用者が居宅介護支援を受けられないというケースも出ている。
だからといって、そのことで利用者が介護保険サービスを受けられなくなるわけではない。セルフプランでサービスを利用するという手があるし、居宅サービス計画書(ケアプラン)が作成されないことを前提にした償還払いでサービス利用するという手もある。(※介護保険法では居宅サービス計画書は保険給付の要件ではなく、償還払いサービスを現物給付化する手段とされている)
しかし、居宅ケアマネは単にケアプランを作成するケアプランナーではない。相談援助職として利用者に寄り添い、ケアマネジメントという手法を使って利用者の生活課題を見いだし、解決する専門家である。そうした対人援助の専門家の支援を受けることができない地域住民が増えているということ自体が問題なのだ。この状態は、国民の福祉を低下させる問題であると言っても過言ではない。
■原因は明白
(残り2680字 / 全3543字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】