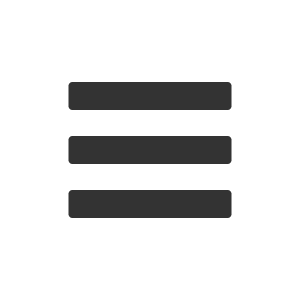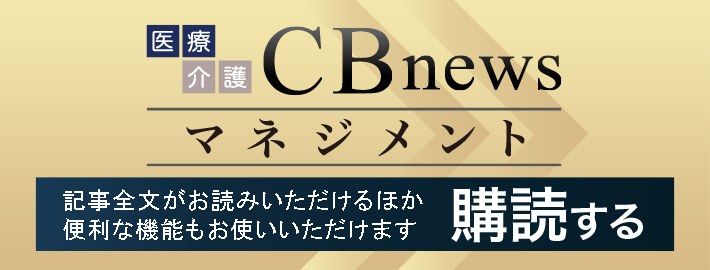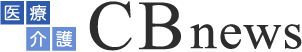CBnewsでは、医療経営の厳しい現状や国への要望を病院のトップから募り、緊急寄稿「病院危機」として配信している。第3弾は、埼玉県済生会川口総合病院の佐藤雅彦院長。(随時配信)
【社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県済生会川口総合病院 佐藤雅彦院長】
日本の医療は、国民皆保険制度やフリーアクセス、高額療養費制度など、優れた仕組みによって成り立っています。貧富の差にかかわらず、全ての国民がほぼ同等の医療を受けられます。一方で、少子高齢化が進む日本では生産年齢人口が減少し、医療制度を含む多くの仕組みにおいて財源が不足しています。 かつて治療が難しかった病気も、今では治せるようになったものが増え、医療の進歩は明らかです。当然、その分医療費は膨らみ、社会保障費も年々増加しています。非効率的で無駄な医療費も存在するのは事実であり、それならば診療報酬でより厳しく制限をかけるべきです。
かつて治療が難しかった病気も、今では治せるようになったものが増え、医療の進歩は明らかです。当然、その分医療費は膨らみ、社会保障費も年々増加しています。非効率的で無駄な医療費も存在するのは事実であり、それならば診療報酬でより厳しく制限をかけるべきです。
財務省は医療・福祉関係の費用を抑えようと必死です。加えて、このような状況の中、厚生労働省は効果が確実とは言い難い高額薬剤を保険適用にしています。これはあまりにも軽率で、愚かな判断だと感じざるを得ません。
今こそ国は日本の医療体制、そして国民皆保険制度を「維持するのか、やめるのか」決めるべきです。維持するのであれば、必要な財源を何らかの形で確保しなければなりません。国防費や公共事業関係費も重要ですが、国民の医療費も大事です。一般会計歳出にはまだまだ無駄があり、切り詰められると思いますが、捻出できないと政府が言い張るならば、消費税増税の手もあるのではないでしょうか。
政府の「骨太の方針」ではこれまで、社会保障関係費の実質的な増加を高齢化分にとどめるとされていますが、医療の進歩による医療費の増額や近年のインフレ傾向は無視されています。政府は一般会計から社会保障費の総額を決め、それから逆算して診療報酬を改定しています。
多くの医療機関は公定価格による保険診療を行っており、必要な出費に対して価格転嫁ができません。物価や人件費の増加が続く中、どこの病院も経営が厳しくなるのは当然です。特に高度な医療を行う病院では、設備投資や診療材料の負担が大きく、人的資源も多く抱えるため、その影響は大きいです。
このように、何とも理不尽な方針の下で犠牲になっているのは病院です。病院が国民にとって必要不可欠なインフラであるならば、「何か要因がある」「経営努力が足りない」というのならまだしも、多くの病院の経営が厳しくなるような国の施策はどう考えてもおかしいと言わざるを得ません。このままでは多くの病院が経営破綻し、医療崩壊につながります。その時、必要な医療を受けられずに困るのは国民です。
人口が減る日本においては、今までと同じ医療体制が必要なわけではありません。中長期的な人口構造や、地域のニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化と連携を進め、良質で適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的とした地域医療構想を、もっと迅速かつ厳格に進めるべきです。
医療のさまざまな施策を決定しているのは厚労省? 財務省? それとも政治家? もう少し適正な対応を求めたいところです。
(残り0字 / 全1311字)
【関連記事】