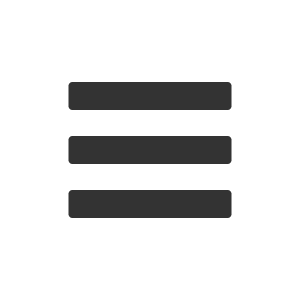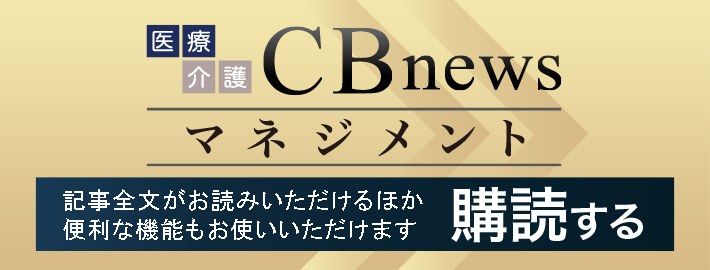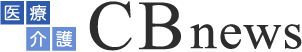【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
政府が6月13日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太の方針2025)には、医療・介護・障害福祉などの公定価格分野の賃上げや、医療・介護・保育・福祉などの公定価格の引上げが明記された。この方針が2026年度予算に反映されるとされたことから、物価と人件費の高騰に対応する期中改定(27年度報酬改定時期を待たずに実施される臨時の改定)の期待が介護関係者の間で高まっている。
しかし、骨太の方針2025には同時に、「歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続」や、「利用者負担の判断基準の見直し等の給付と負担の見直しに関する課題について、2025年末までに結論が得られるよう検討」という文言も盛り込まれ、利用者負担の2割対象者の拡大や居宅介護支援費の自己負担導入、軽介護者の訪問・通所介護の地域支援事業化などを示唆する内容も書かれている。
このように介護報酬の引き上げには国民の痛みが伴う。果たして、そのことを全ての国民が納得して受け入れてくれるだろうか。そう考えると、今後の介護事業経営に必要な財源支出の訴えを正論化するためにも、介護事業が国民の暮らしを支えるセーフティーネットであることを示す必要があるといえる。
しかし、介護事業での虐待や人権侵害が月単位で報道されているという実情がある。そのため、報道される介護事業者の虐待事件は「氷山の一角」に過ぎず、表面に出ていない虐待が数多くあるのだろうと考える人が増えている。その中には介護事業を「必要悪」という声もある。利用者への虐待は介護事業に対する国民の信頼を損ね、今後継続して必要とされる国の財源支出への反対の声につながりかねない。だからこそ、介護事業関係者は襟を正して介護事業での虐待や人権侵害をなくす不断の努力が必要だ。
■選ばれる事業者となるには
そのためには、このような人権侵害を伴う事件がなぜ起きるのかという根本原因を考えなければならない。介護支援を
(残り2947字 / 全3779字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】