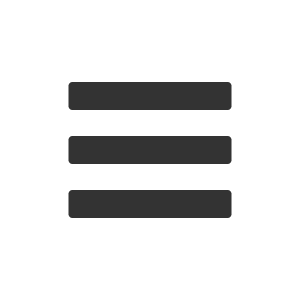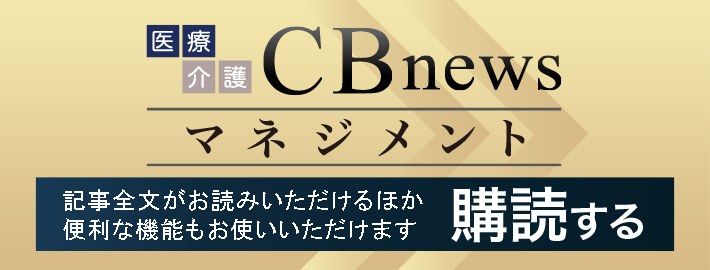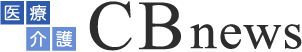【久留米大学病院薬剤部副部長 有馬千代子】
2014年度の診療報酬改定において後発医薬品の使用を推進すべく要件が強化された。診療群分類別包括制度(DPC)病院においては、入院医療に用いる後発医薬品の使用促進を評価するものとして数量シェアが評価指標となった。そのため、各DPC病院は入院での数量シェア60%の評価上限を目指して検討していることであろう。
移行期間は先発医薬品と後発医薬品の併用採用も試みるなど、試行錯誤を繰り返した。時を少し経て、07年度には福岡県ジェネリック医薬品使用推進協議会が発足し、モデル病院として、一層、後発医薬品の取り組みを強化することになった。
厚生労働省は今年、13年度の日本人の平均寿命は女性86.61歳、男性80.21歳と男性も80歳を超え、男女共に過去最高を更新したと発表した。急速な少子高齢化が進む中、わが国の保険医療はパンク寸前である。福岡県は県民1人当たりの医療費が全国平均に比べて高く、老人医療費は全国で上位を占める。このため、後発医薬品を使用することで、圧迫している医療経済を少しでもよい方向へ導かなければならないと考えている。
(残り1466字 / 全2174字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】