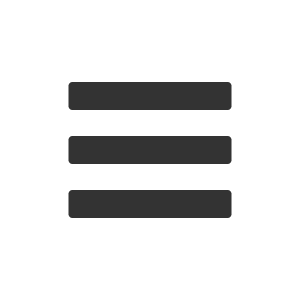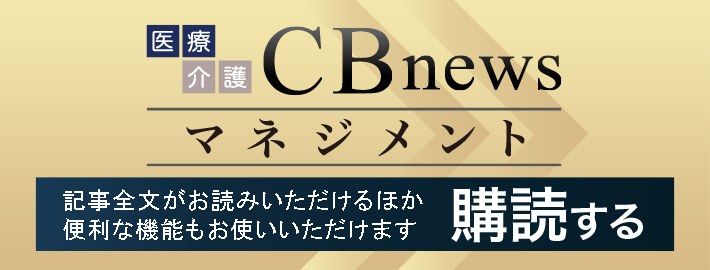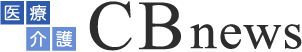【株式会社コミュニケーション・ケア代表取締役 水上朝雄】
改正医療法で都道府県に設置が求められている「医療勤務環境改善支援センター」の全国第1号となった福岡県から、前回はセンターの概況をお伝えしました。今回は、これから本格的に行っていく勤務環境改善の支援のポイントについて述べたいと思います。
■勤務環境改善には「お互いさま」が大切
ある病院では、会議で勤務環境改善に関する議題が取り上げられた時、出席していた医師が「まずは、おれたちの勤務環境を改善してくれよ!」と言ったために皆が黙ってしまい、その後、誰もその話題を議題に挙げなくなったそうです。確かに医師の勤務環境は最悪の場合が少なくありません。むしろ医師の勤務環境改善を真っ先にできるくらいであれば、他職種の勤務環境改善も難しくないのかもしれません。しかし、何とか苦労して医師の数を増やすことに成功したとしても、それに見合った収入が伴わなければ、人件費の増加がただでさえ苦しい経営を圧迫しかねないのです。
(残り2376字 / 全3039字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】