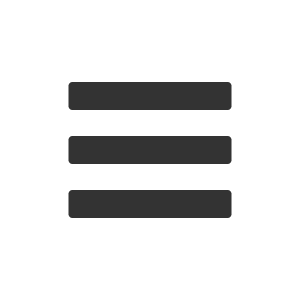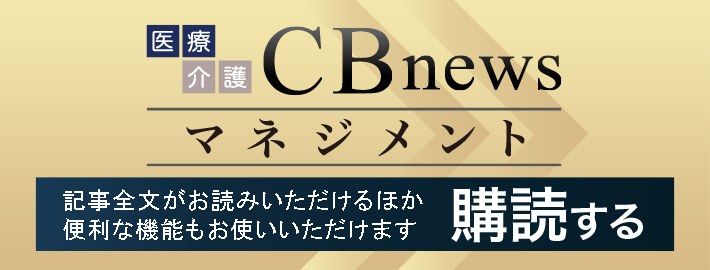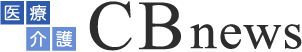官民を挙げてICT(情報通信技術)の活用に力を入れる中、救急車から患者のエコー画像を伝送したり、医療者向けの講習が開かれたりするなど、遠隔医療を取り巻く環境が変わりつつある。医師が旗振り役となって進めてきた遠隔医療の分野に、ここ数年は大学や患者団体、ベンチャー企業などが参入。2月に開かれた日本遠隔医療学会の会合では、患者団体の代表者が“主役”の1人として発表した。遠隔医療に詳しい酒巻哲夫・群馬大名誉教授は「遠隔医療を発展させるには、患者の声に医療者が耳を傾けることが大事」と話している。【新井哉】
■遠隔操作の超音波プローブ、実用化向けデータ収集
患者を搬送中の救急車から診療関連のデータを病院に伝送する―。2000年代後半から各地で本格的な実証実験が行われてきたが、失敗や不具合が生じるケースが続出。ここ数年、ようやく実用化に向けた取り組みが出てきつつある。神奈川県内で今月4日に行われた同県の「さがみロボット産業特区」の重点プロジェクトの実証実験も、実用化が有力視される取り組みの1つだ。
このシリーズの(2)の記事は来月配信する予定です。
■遠隔操作の超音波プローブ、実用化向けデータ収集
患者を搬送中の救急車から診療関連のデータを病院に伝送する―。2000年代後半から各地で本格的な実証実験が行われてきたが、失敗や不具合が生じるケースが続出。ここ数年、ようやく実用化に向けた取り組みが出てきつつある。神奈川県内で今月4日に行われた同県の「さがみロボット産業特区」の重点プロジェクトの実証実験も、実用化が有力視される取り組みの1つだ。
このシリーズの(2)の記事は来月配信する予定です。
(残り1435字 / 全1906字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】