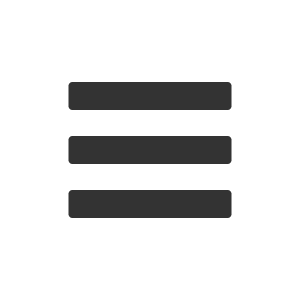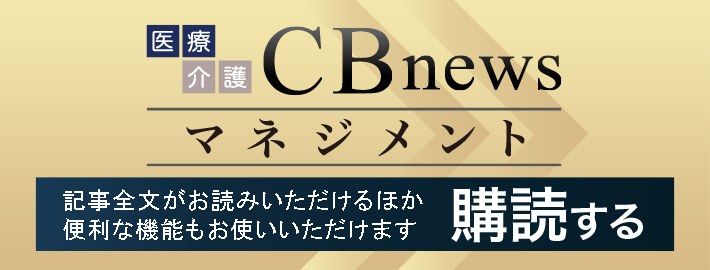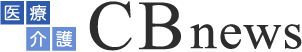【千葉大学医学部附属病院 副病院長、病院経営管理学研究センター長 、ちば医経塾塾長 井上貴裕】
前稿では転院先がないために在院日数が長期化するケースがあり、全国のDPC対象病院における傷病名別の転院率なども明らかにした上で、今後の医療連携の在り方について取り上げた。そこでは連携パスが機能する疾患では転院率が高いが、今後増加するであろう高齢者救急については必ずしも転院が多くなく、入院を長期化させる一要因となっていることが分かった。
このことに関連して、2024年度診療報酬改定において救急患者連携搬送料が新設され、高度急性期病院で救急の初期診療を行った後に、連携先医療機関に医師、看護師または救急救命士が同乗の上、搬送した場合の評価が行われている。高次医療機関で入院させず転送した場合の評価が最も高く1,800点であり、入院3日以内の転院の場合には600点という設定になる。診療報酬で評価されれば、各医療機関も「下り搬送」、あるいは「連携搬送」をできるだけ実現しようと取り組みを行っている最中であると予想する。ただ、下り搬送は容易でないという現実もあり、本稿ではかつて存在した救急搬送患者地域連携紹介加算の状況を振り返った上で、下り搬送を有効に機能させるために求められる要件について私見を交えて考えていく。
(残り2443字 / 全2992字)
次回配信は3月24日を予定しています
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】