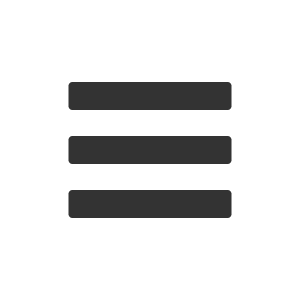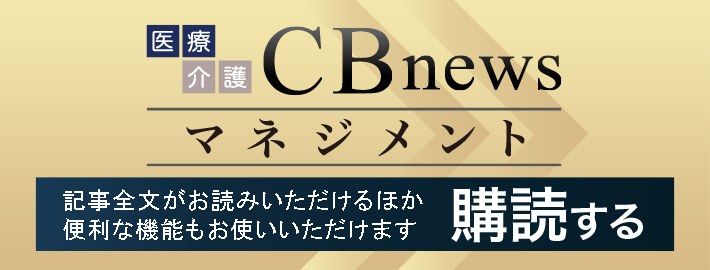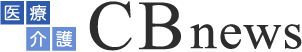CBnewsでは、医療経営の厳しい現状や国への要望を病院のトップから募り、緊急寄稿「病院危機」として配信している。第2弾は、JA愛知厚生連足助病院・小林真哉院長。(随時配信)
【JA愛知厚生連足助病院 小林真哉院長】
愛知県西三河北部医療圏のへき地医療拠点病院である足助病院の使命は、この地に病床を持つ医療機関として存在し続けることだと思い、一人の医師として、経営・管理を担う病院長として日々を過ごしています。物価・人件費・材料費・維持費の高騰に診療報酬の上昇が追いつかないのは周知の事実です。この辺りは、小医・中医・大医でいう大医を担う方々に委ねるとして、小-中を司り身に染みて感じていることを記します。 時代はVUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity)で予測困難な様相を呈しています。医師の働き方改革に代表されるように、労働者としての医療従事者の立場が確立されてきたことは喜ばしいことですが、一面、人件費高騰に拍車をかけていることも事実です。さらには、コロナ禍3年間の影響もあり、人としての働き方への考え方が変化したこと、Z世代の人生観も相まってリクルートにも変化が出ています。
時代はVUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity)で予測困難な様相を呈しています。医師の働き方改革に代表されるように、労働者としての医療従事者の立場が確立されてきたことは喜ばしいことですが、一面、人件費高騰に拍車をかけていることも事実です。さらには、コロナ禍3年間の影響もあり、人としての働き方への考え方が変化したこと、Z世代の人生観も相まってリクルートにも変化が出ています。
当院に関しては、へき地医療や在宅医療・総合診療に興味を持つ若手医師が増えてきたことや自治医科大学の派遣医師・地域枠医師の派遣など国の施策の恩恵にあやかり、医師は比較的充実してきました。高度な医療や救急体制は提供できませんが、2040年へ向けての地域医療構想に乗って、豊田加茂医療圏の医療機関との連携強化し、身の丈に合った医療・福祉・介護のシームレスな医療提供を継続しています。ただ、病院は医師だけでは運営できません。さまざまな専門職・事務に支えられるチーム医療が必要です。
そして今、国の試算でも出ていますが、看護・介護人材不足がまさに「病院危機」の引き金になりかねない状況にあります。われわれのようなへき地では、かつて高齢化の波が最初に訪れたように今、人材不足の荒波が既に押し寄せています。病床数に対して予算が組まれ要員が設定されるので、要員が充足して地域が求める病床を用意できれば病床が埋まり、経営も安定するわけです。現状は、ヘルスケア産業の隆盛・リクルートエージェントの闊歩・人生観の変化などで要員維持が困難になっています。これからの時代はナイチンゲールの奉仕の理念だけでは立ち行きません。看護師・介護士不足の解消は一朝一夕では困難でしょう。
かつて、医師不足に対して医学部創設や地域枠拡充などの施策を行い40年には医師数は充足するビジョンが示されました。長い目で見たビジョン・教育が必要だと思います。ぜひ、大医を担う方々にはコメディカルの人材不足にもさらに注視していただきたいと思います。
最後に「院長は孤独だ」と俗に言われますが、私自身は、温かく優秀な職員と温かく病院を見守る地域住民に支えられています。さらに心強いのは、豊田市行政および病院の運営母体であるJA愛知厚生連の素敵なサポートがあります。命題-2040年にこの地でこの姿で当院を運営できているかどうか-。われわれの挑戦は続きます。
(残り0字 / 全1313字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】