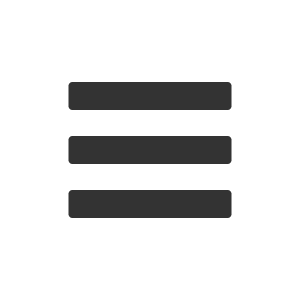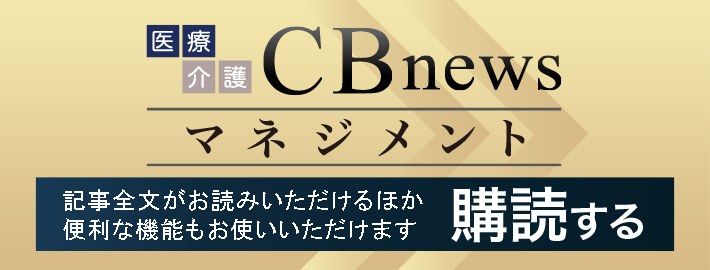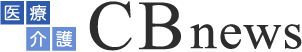【株式会社MMオフィス代表取締役 工藤高】
■DPC/PDPSは成熟化して、今後は義務化の議論が加速する
2003年度にDPC/PDPSの急性期1日当たり定額払い制度が導入されてから丸10年以上が経過した。日本の入院医療における効率化や質の向上について一定の評価ができるレベルにまで、DPC/PDPSは成熟しつつある。次回14年度診療報酬改定では、恐らく7対1入院基本料や亜急性期入院医療管理料といった入院料の基本的な部分の大変革があるが、DPC/PDPSに対しては、診断群点数の変更や包括対象の薬剤見直し、機能評価係数2の若干の見直し等の細かな変更にとどまるだろう。前年度収入保証の調整係数(暫定調整係数)の18年の完全廃止に向け、制度の信頼性・透明性を粛々と高めていくに違いない。
今回はDPC/PDPSにおいて症例数の多い疾患の一つである誤嚥性肺炎について、先日、中央社会保険医療協議会のDPC評価分科会で公表された12年度公開データを基に考察してみる。
(残り1716字 / 全2386字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】