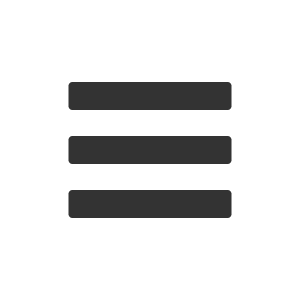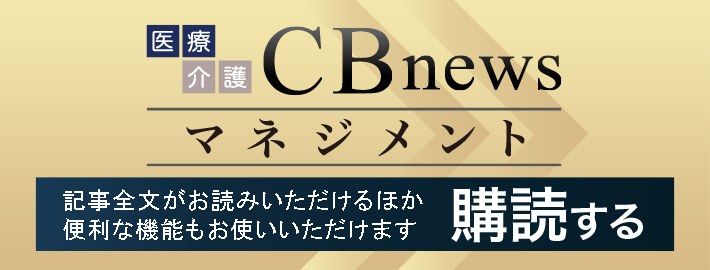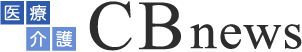【株式会社MMオフィス代表取締役 工藤高】
■ケースミックス無視の在院日数短縮は限界ではないか
これまで在院日数短縮の議論は、社会保障・税一体改革において「医療資源の投入強化等による機能強化、医療機関間や医療と介護の連携の強化等により、平均在院日数の短縮」を図ることがうたわれ、社会保障制度改革国民会議においても所要額(公費)が4400億円程度削減できるとされてきた。その一方で、現場からはこれ以上在院日数は短縮できないとも言われ、「診療報酬で機能分化を進めるのがあまりに性急で、地域の医療が崩壊してしまう」「平均在院日数を短縮する努力は惜しまないが、特定除外患者のような制度上行き場のない患者の受け入れ負担は医療機関個別の問題ではないはず」「在院日数を短縮した結果、ベッドが空いてしまい経営が成り立たない」といった悲鳴や嘆きの声を聞く。
■在院日数短縮には4つの指標を考慮しないといけない
現状の平均在院日数算定式で限界点を超えるには、以下の4つの指標がカギになる。それぞれが在院日数にどのような影響を与えるか、データから考えてみたい。
① ケースミックス(患者構成)
② 年齢
③ ADL(日常生活動作)
④ 認知症
次回配信は4月1日5:00を予定しています
(残り2383字 / 全3392字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】