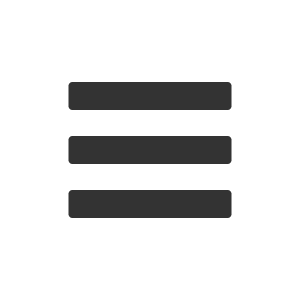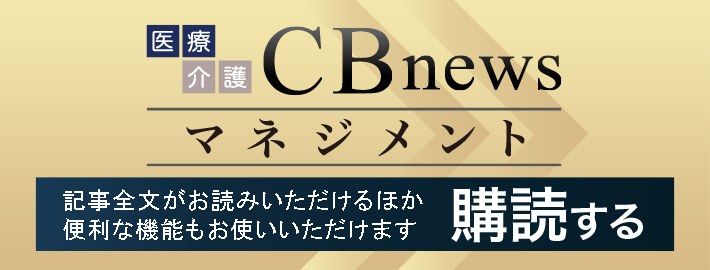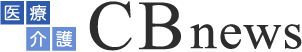【「待合室から医療を変えようプロジェクト」リーダー 河内文雄(医療法人社団以仁会理事長)】
医食同源という言葉があります。主として漢方の領域で用いられ、若干のうさんくささも伴うことから、その言葉を知ってはいても、普段から意識して生活しているという人はあまりいないのではないかと思います。しかし、急性疾患であれ慢性疾患であれ、患者さんは「この病気は、何を食べればいいですか?」と判で押したように質問してきます。
実は私も急性膵炎で入院したことがあり、退院後の食事療法に難儀したことがあります。食べる側の私も参りましたが、食事を作る家族はもっと大変だったようです。膵炎食は非常に制限が多いので、その範囲内で飽きないようにさまざまなメニューを考えることは、素人には大変な作業だっただろうなと(今になると)思います。
(残り2032字 / 全2595字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】