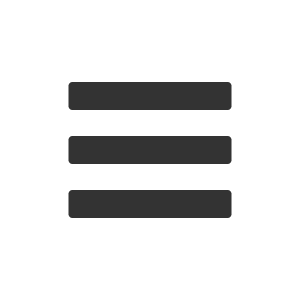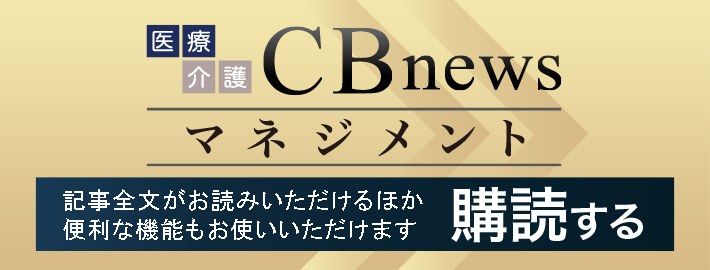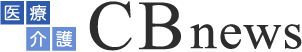在宅歯科医療をめぐる課題や今後の方向性について議論した中医協総会(11日、厚労省)
中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)は11日の総会で、在宅歯科医療をめぐる課題や今後の方向性について議論した。厚生労働省側は、2010年度の診療報酬改定で、同一建物内の患者数と訪問診療の時間(20分以上)を評価する体系に見直した「歯科訪問診療料」について、対象者の要件などを論点として示した。
一方、厚労省の調査によると、施設で訪問診療を行っている歯科診療所は増加したものの、居宅で歯科診療を実施している診療所は減少。また、08年度の報酬改定で創設された「在宅療養支援歯科診療所」の届け出数も伸び悩んでいる。
こうした現状を踏まえ、厚労省はこの日の総会で、▽歯科訪問診療料の評価体系を見直すべきか。また、対象者の要件をどう考えるか▽一度に複数の患者に行う訪問歯科診療の評価をどう考えるか▽在宅歯科医療における医療機関と介護の連携に関する評価をどう考えるか▽在宅療養支援歯科診療所の評価をどう考えるか▽訪問歯科診療を行う際の歯科衛生士の補助に関する評価をどう考えるか―の5つの論点を示した。
診療側の堀憲郎委員(日本歯科医師会常務理事)は、「特に居宅に対する評価が、今止まっているので、その評価と、1人の患者さんに対する訪問診療、こういったところを確実に評価していただきたい」と要望。また、在宅療養支援歯科診療所の役割と機能の明確化や、歯科衛生士に関する評価も求めた。
(残り0字 / 全747字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】